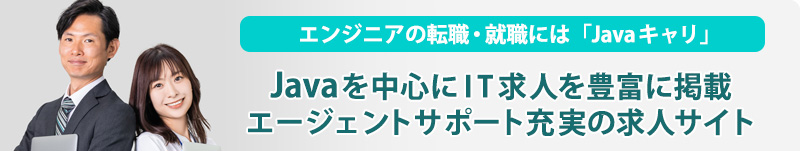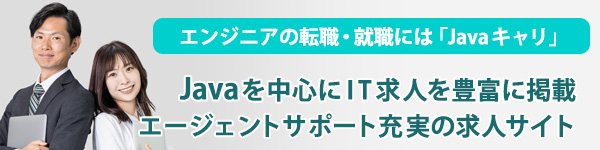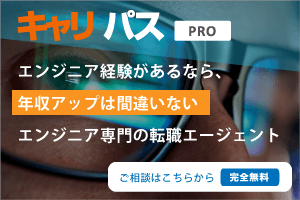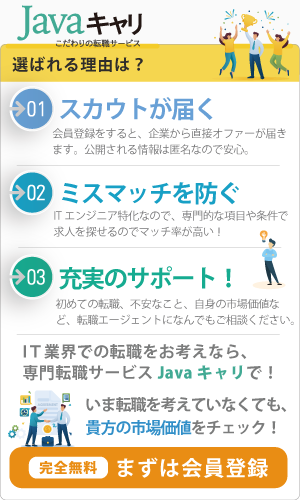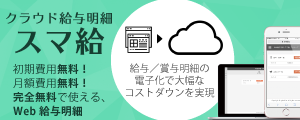HTML5は、W3Cが定めたHTMLの勧告のことですが、2021年1月28日に廃止されました。
Webエンジニアにとっては、すでに知られたニュースですが、エンジニアであっても知らなかったという人が多いのではないでしょうか。
webサイトのフロントエンドを構築する上でも欠かすことのできないHTMLとCSSですが、既に一般的となっているHTML5が何故廃止となったのでしょうか。
モバイル用のwebサイト、PC用のwebサイトを切り分けたりする上でもHTML5は非常に便利なものでしたし、今では誰もが当たり前のように使っています。
順当に行けば次はHTML6になるのではと思っていた人も多いのではないでしょうか。
しかし、2021年1月には廃止というだけではなく、なんとW3Cの策定ではなく、WHATWGと言う組織が策定したHTML Living Standardに切り替わったのです。
どうしてこんなことになったのでしょうか?
今回の記事では、現在も利用できているHTML廃止の廃止とはどういうことなのか、何故廃止されたのかについて解説します。
また、では、これからHTMLはどうなるのかについても触れていきます。
Contents
そもそもHTML5とは?

HTML(Hyper Text Markup Language)とは、Webサイトのコンテンツを作るために使用するマークアップ言語です。
HTML5は、HTMLの改訂第5番のことで、2014年に発表されておりホームページ制作に欠かせないものになっています。
HTML5はHTML4よりも機能が多く、とても便利になっています。今まで複雑だった処理が比較的容易にでき、HTMLをよりスッキリかけます。
Webで動画を使用するとなれば、従来まではFlashを埋め込んで利用するのが主流でしたがHTML5では「video要素」というものが出来ました。video要素を使用することにより、シンプルに動画を扱えるようになりました。
他にも便利な機能をたくさん持っていたHTML5ですが、2021年1月28日に廃止され、「HTML Living Standard」が標準となりました。
HTML5が廃止された経緯
HTML5はW3Cという組織が策定していましたが、このHTMLの標準仕様をWHATWGという組織が取り決めることになりました。そしてこのWHATWGが決めるHTMLの標準仕様がHTML Living Standardです。
当初、別々に独自の仕様を策定して活動していたW3CとWHATWGは寄り添って共同開発を始めました。共同開発を進めるうちに、考えの違いなどで徐々に乖離していき、WHATWGは2011年にHTML Living Standardを開始、2012年には共同開発を中止し、W3Cは2016年にHTML5.1を独自に勧告しました。
その辺りから、Google・FireFox・SafariなどのブラウザではHTML Living Standardを標準仕様として採用するようになり、いずれEdgeも移行を発表しました。
これにより、W3CはHTML5を標準化することを断念し、今後のHTML標準化をWHATWGに委ねたのです。
HTML Living Standardとは
HTML Living Standardとは、2019年よりHTML技術仕様の標準規格です。
これまでは、W3Cという組織が策定したHTML5がHTMLの標準規格でした。
新しく採用されたHTML Living Standardは、Apple・Mozilla・Operaの開発者によって設立されたWHATWGという組織が策定しています。WHATWG HTMLと呼ばれることもあります。
この、HTML Living Standardの仕様は、HTML5の廃止によって採用されたものです。一部のタグの扱いが変更になっているので、HTML Living Standardの基礎やHTML5との違いについて理解していなければ、不適切なマークアップをすることになり、SEOへの影響が懸念されます。
HTML5とHTML Living Standardの違い
基本的なHTMLを書く上では、HTML5とHTML Living Standardに大きな違いはありません。
しかし、HTML Living Standardで新たに追加された点や変更されている点はあります。
- <a href=””>をクリックした際に、hrefのページに遷移しつつも、別のURLにpingを送信するping属性の追加
- 見出しのグループ化を行う<hgroup>の追加
- <cite>で創作物のタイトル以外を含むことができず、作者名を含むことができないように変更
- <link>で”rel”属性の値が”body-ok”な値のみの際、または”itemprop”属性が指定されている際に”body”の要素内に配置できるように変更
- <meta>で”itemprop”属性を指定した際は”body”要素内に配置できるように変更
- <style>が”body”要素内に配置できないように変更
- 先頭の文字を大文字化するか指定する「autocapitalize=””」グローバル属性の追加
- ソフトウェアキーボードの[Enter]キーのアイコンを指定する「enterkeyhint=””」のグローバル属性の追加
- カスタム要素と関連づける「is=””」のグローバル属性の追加
- 自動フォーカスの可否を指定する「autofocus=””」がグローバル属性として定義されるように変更
- 入力する際のソフトウェアキーボードの種類を指定する「inputmode=””」がグローバル属性として定義されるように変更
上記は一部ですが、一部のタグの扱いが違うだけで、そこまで大きな変更はありません。
HTML Living Standardに対応してるWebブラウザ

HTML Living Standardに対応しているWebブラウザは、主にGoogleのChrome、MozillaのFirefox、AppleのSafari、Operaです。
HTML5が廃止される経緯にもあった通り、2016年ごろから、GoogleのChrome、MozillaのFirefox、AppleのSafari、Operaの主要ブラウザがW3Cに準拠することをやめ、HTML Living Standardを採用し始めたことが関連しています。
それらに加えて、唯一W3C派だったMicrosoftのEdgeもChromeと同じベースに移行することを発表しています。
CSS3はどうなっているのか?
HTML5が廃止されたことによって、気になるのがCSS3についてです。HTML5と共存しているように思われがちなCSS3は、今もなおW3Cの管轄です。
実装と勧告のスピードの違いが問題視されていたHTML5ですが、CSSはHTMLとは違い、機能単位でアップデートする方針で進めていたことが関係しているかもしれません。
HTMLを学ぶにはどうすればいいのか?

これからHTMLを学ぶには、HTML Living Standardの仕様で書いてある本で学習を進めましょう。
新規で追加されたタグやHTML5から廃止されたタグの代替方法について知っておきましょう。
ただし、これまでHTML5の学習をしていた場合も、決して無駄になるわけではありません。HTML Living Standardの仕様になったとしても、HTMLのベースは大きく変わらないからです。
HTML Living Standardを理解する上でも、HTML5の知識は、学習する上でとても有効的です。
HTML Living Standardの基礎を知らなければ、不適切なマークアップをおこなってしまう可能性が高まります。
そうなると、クローラーが理解しづらかったり、レイアウトの崩れによってユーザビリティの低下につながるかもしれません。結果、コンテンツ自体の質が低下してGoogleより評価されづらくなります。
最悪の状況を回避するためにも、HTML5とHTML Living Standardの違い、そして基礎を把握して適切にサイトを構築しましょう。
まとめ
HTMLの規格策定はW3Cから、WHATWGが策定することに変わりました。すなわち、HTML5は廃止されて、これからはHTML Living Standardが主流になったのです。
これからHTMLの記述でわからないことや、新たに学ぼうとするときはHTML Living Standardの仕様書などを読むことで正しいHTMLを習得できると理解しておくといいでしょう。
また、HTML5の学習が無駄になるということはありません。HTML Living Standardを理解する上でもHTML5の知識は非常に有効なのです。
これまではHTML5とHTML Living Standardがダブルスタンダードのような扱いで、迷ってしまうようなこともありましたが、今後は統一されることになったわけですからエンジニアとしてはわかりやすくなったと思えば、決して悪いことではありません。
注意が必要なのは、HTML Living Standardは頻繁に仕様が改訂されています。エンジニアとしては情報を漏らさず仕様を理解することをおすすめします。