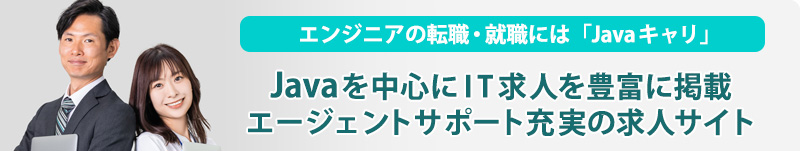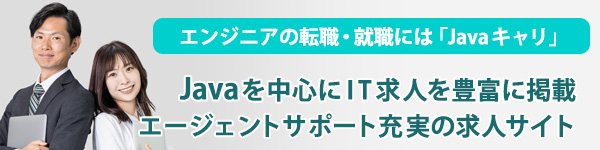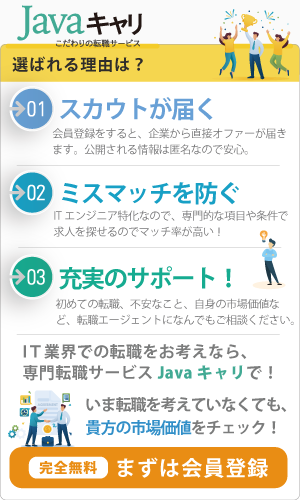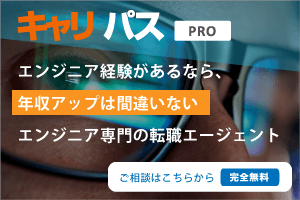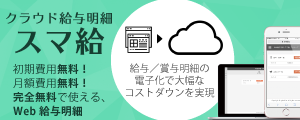Webサービスやアプリケーションが溢れる現代。これらの裏側では、様々な種類のエンジニアが活躍しています。
その中でも、近年注目を集めているのが「フルスタックエンジニア」です。一体、フルスタックエンジニアとは何者なのでしょうか?
この記事では、その魅力と可能性について深掘りしていきます。
■□■□プログラマーなどITエンジニアを目指しているならIT業界専門転職サイト「Javaキャリ」が最適!完全無料の会員登録はこちらから■□■□
Contents
フルスタックエンジニアとは
フルスタックエンジニアとは、システムの開発プロジェクトで複数の役割を担うエンジニアです。フロントエンドヤバックエンド、インフラ、など、システム開発の各工程でオールラウンドに活躍できます。
そのため、仕事内容は多岐にわたり、プロジェクト全体を通じて重要な役割を担うメンバーとなります。
フルスタックエンジニアの強み
フルスタックエンジニアの主な強みを3つ紹介します。
1つ目は開発スピードの短縮です。複数の工程を一人で担当するため、前工程からの引き継ぎや状況把握が不要になるため、迅速な開発が可能になります。
2つ目は人件費の削減です。複数の高度なスキルを持つため、専門エンジニアを複数雇用する必要がないため、コスト削減につながります。
3つ目はコミュニケーションミスの減少です。他のエンジニアの関与が少なくなるため、コミュニケーションミスが少なくなります。
フルスタックエンジニアの仕事内容
フルスタックエンジニアの仕事内容は多岐にわたります。フルスタックエンジニアの主要な仕事内容を紹介します。
フロントエンド
フロントエンドとは、ユーザーが直接触れる部分の開発を指します。
主な開発は、Webサイトのレイアウトやボタンの配置などの設計・実装です。
HTMLやCSS、JavaScriptなどのプログラミング言語を用いて、UIと呼ばれるユーザーインターフェースの範囲が担当になります。
バックエンド
バックエンドとは、サーバーサイドの処理を担当します。
データベースの設計やサーバーの設定などを行います。
JavaやPython、PHPなどのプログラミング言語や、Oracleをはじめとするデータベース管理システムについてのスキルが求められます。
アプリ開発
モバイルアプリケーションやデスクトップアプリケーションの開発を行います。
iOSやAndroid向けのアプリ開発では、SwiftやKotlinなどのプログラミング言語を使用することが一般的です。UXと呼ばれるユーザー体験を重視した設計・実装が求められます。
インフラ
インフラとは、システムが稼働する基盤の構築・運用を指します。
サーバーの設定やネットワークの構築、AWSをはじめとするクラウドサービスの利活用などが含まれます。高可用性やセキュリティについての知識が重要です。
デザイン
デザインでは、ユーザーインターフェースやユーザーエクスペリエンスのデザインを行います。
色彩設計やレイアウト、タイポグラフィなど、視覚的な要素を考慮しながら設計し、ユーザーにとって使いやすいデザインを追求する必要があります。
フルスタックエンジニアに必要なスキル

フルスタックエンジニアとして活躍するためには、以下のスキルが求められます。
プログラミング
フルスタックエンジニアは各分野で使用されるプログラミング言語の習得が必要です。
例えば、JavaScriptやPython、Java、PHPなどが挙げられます。どの分野もプログラミング言語を使用するため、安定したプログラミング能力が必要になります。
データベース
データの管理・操作に関する知識が求められます。
MySQLやOracle、PostgreSQLなどのデータベース管理システムの使用経験はもちろん、SQLの理解が重要です。データベースの設計やエラー時の対応も必要になります。
OS・ミドルウェア
LinuxやWindowsなどのOSの知識、ミドルウェアの設定・運用経験が必要です。
ミドルウェアは多くの種類があるため、複数種類の仕様を理解しなくてはいけません。これらの知識は、システムの安定稼働に寄与します。
ネットワーク
TCP/IPやHTTP、DNSなどのネットワークプロトコルの理解をはじめ、ルーターやスイッチの設定、ネットワークセキュリティの知識が求められます。
ネットワーク回線が重くなるとシステム利用に影響を及ぼすため、ネットワークも重要な分野です。システム間の通信を円滑にするためのスキルが必要になります。
クラウドサービス
AWSやAzureなどのクラウドサービスの利用経験が求められます。
仮想マシンの作成からストレージの管理、クラウド環境での開発・運用スキルが重要になります。IT技術では、比較的新しい知識ですが、利用企業が年々増加しているため、必須のスキルといえます。
セキュリティ
システムの脆弱性対策やデータ保護など、セキュリティに関する知識が必要です。
安全なシステム運用のための基本的なセキュリティ対策を理解し、実践できる能力が求められます。近年の高度化したサイバー攻撃に対応するスキルも必要になります。
要件定義・設計
クライアントの要求を正確に把握しシステム要件として定義する能力、設計を行うスキルが必要です。開発プロジェクトの上流工程から参画し、全体の方向性を決定する重要な役割を担います。
マネジメント
開発プロジェクトの進行管理やメンバーとのコミュニケーション、リソースの配分などのプロジェクトマネジメント能力が求められます。
プロジェクトマネージャーのように全体を俯瞰し、プロジェクトを効率的に進行させる能力が重要です。
フルスタックエンジニアの年収
一般的なシステムエンジニアやプログラマーの平均年収と比較して、フルスタックエンジニアの年収は高い傾向にあります。
なぜなら、フルスタックエンジニアは幅広い領域の知識とスキルを有してなければ難しい職種だからです。
ただし、スキルや経験、担当するプロジェクトの規模や難易度によって、年収は大きく異なります。
なぜフルスタックエンジニアが求められるか
近年、開発手法の変化やクラウドサービスの普及により、フルスタックエンジニアの活躍の場が増えています。
サービスをスモールスタートし、継続的に機能をリリースするビジネス戦略を取る企業が増え、短いスパンで繰り返し開発したり、短期間にサービスを立ち上げたりすることが多くなりました。
そのため、複数の分野に精通し、柔軟に対応できるフルスタックエンジニアの需要が高まっています。
フルスタックエンジニアの転職市場
フルスタックエンジニアの転職市場は、需要が高まっています。
特に、規模が小さい企業やスタートアップ企業、ベンチャー企業では複数の分野における問題の解決やスピード感のある事業立ち上げが求められるため、フルスタックエンジニアの存在が重要視されています。
一方、規模が大きい企業でも、人員が足りていない部門への配置や、新規プロジェクトの立ち上げ時にフルスタックエンジニアが求められるケースがあります。
そのため、フルスタックエンジニアとしてのスキルや経験を持つ人材は、幅広い企業からの求人が期待できます。
フルスタックエンジニアの将来性
フルスタックエンジニアは、複数の職種を一人でまかなえるため、市場価値の高い人材です。
そのため、フルスタックエンジニアの需要は今後も高まり続けると予想されます。
複数職種をまかなえることによる優位性
フルスタックエンジニアは、フロントエンドやバックエンド、インフラなど、さまざまな分野の知識とスキルを持ち合わせています。
そのため、プロジェクト全体を俯瞰し、効率的に開発を進めることが可能です。
フロントエンドエンジニアとバックエンドエンジニアが別々に存在する場合、コミュニケーションの齟齬や作業重複が発生する可能性があります。
しかし、フルスタックエンジニアであれば、一人で進めることができるため、開発スピードの向上や品質維持に貢献できます。
市場での需要はなくならない
IT技術は日々進化しており、新しい技術やサービスが次々と登場しています。
その中で、フルスタックエンジニアは多様なスキルセットを持つため、変化に柔軟に対応できます。
クラウドサービスの普及に伴い、従来のインフラエンジニアの役割が変化していますが、フルスタックエンジニアはクラウド環境での開発や運用にも保有するスキルで対応可能です。
技術の進化に伴う市場のニーズに応じて、自身の保有するスキルをアップデートし続けることで、需要がなくなることは考えにくいでしょう。
特異で強みがある職種なので競争になりにくい
フルスタックエンジニアは、幅広い知識とスキルを持つため、特定の分野に特化したエンジニアと比較して競争が少ない傾向にあります。
フロントエンドエンジニアやバックエンドエンジニアはそれぞれの専門分野での競争が激しいですが、フルスタックエンジニアは広い範囲のスキルがあるため、独自の強みをアピールできます。
そのため、転職市場でも有利な立場に立ち、将来のキャリアの選択も広げることができるでしょう。
フルスタックエンジニアになる方法
フルスタックエンジニアになるためには、計画的なスキル習得と経験の積み重ねが重要です。具体的なステップを紹介します。
まずは一つの分野で専門性を高める
最初に、フロントエンドやバックエンド、インフラなどから興味のある一つの分野を選択し、専門性を高めましょう。
フロントエンジニアは複数の分野に精通していますが、それぞれの分野について堅実にスキル習得を行った結果です。
まずは、一つの分野の基礎的な知識を身につけ、関連するプログラミング言語を習得し、実務経験を積むことが重要です。
専門領域を広げていく
一つの分野で経験やスキルを習得した後は、他の分野にも挑戦して専門領域を広げます。
例えば、フロントエンドのプログラミングスキルを習得した後は、バックエンドのプログラミング言語を学び、データベースの知識を深めることでシステム全体の理解を深めることができます。
このように関連する分野から広げると学びやすいです。
下流の経験を積む
コーディングやテストなどの下流工程の経験を積むことで、実装力と問題解決能力が向上します。
既存システムの保守や運用、バグ修正などを担当し、プログラミングについてのスキル向上を行うとともに、ユーザーニーズを理解することができます。
上流の経験を積む
要件定義や設計などの上流工程の経験を積むことで、開発プロジェクト全体の流れを把握し、より効果的なシステム開発が可能になります。
クライアントとの打ち合わせや要件の整理、システムアーキテクチャの設計などを経験することで、プロジェクトマネジメントスキルの向上が期待できます。
最新情報のキャッチアップ
IT技術は日々進化しているため、IoTやAIなどの最新技術やトレンドを常にインプットすることが重要です。
日常的にIT業界の最新情報が入ってくるような仕組みを構築し、知識のアップデートを心がけましょう。
例えば、技術記事の購読や勉強会への参加、オンラインコースの受講などがおすすめです。
フルスタックエンジニアの課題
フルスタックエンジニアの課題について紹介します。
スキルの証明が難しく、疑われやすい
フルスタックエンジニアは、スキルの証明が難しいため、疑われやすいという課題があります。
複数の分野、それぞれについてのスキル証明が難しいことが多く、採用側にそのスキルを疑われてしますこともあるでしょう。
可能であれば、複数分野の資格試験取得や過去のプロジェクト経験での開発経験や役割を細かく提示できるようにします。
スキルの広範囲な維持とアップデート
前述した通り、IT技術の進化により、複数分野に関するスキル維持が難しくなる可能性があります。
日々アンテナを張り、実際に技術に触れることで、大幅なアップデートが必要にならないように工夫が必要になります。
効率的な作業分担とチーム内コミュニケーション
フルスタックエンジニアは、複数分野に関する知識やスキルを有していますが、プロジェクト規模により一人で行えるとは限りません。
そのため、プロジェクトメンバーの効率的な作業分担とチーム内コミュニケーションが必要になります。
プロジェクトマネジメントの知識やコミュニケーションスキルを有することで円滑なプロジェクト推進に貢献できるでしょう。
エンジニアは専門領域を広げていくことが求めらえる
いま注目されているフルスタックエンジニアについて、紹介しました。
フルスタックエンジニアの定義は曖昧で、本当にフルスタックエンジニアとしてのマルチなスキルを持っていることの証明は難しいことがわかりました。
しかし、開発手法の変化やクラウドサービスの普及で短いスパンの開発案件や、短期間のサービス立ち上げが求められている今、フルスタックエンジニアは重宝されます。
フルスタックエンジニアへのキャリアパスを目指すには、まずは1つの分野から習得し、多数の分野の知見や経験を広げていく方法が効果的です。
フルスタックエンジニアは他のITエンジニア職よりも需要が高く、年収アップを目指すエンジニアにもおすすめです。