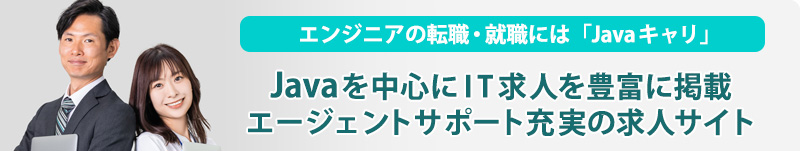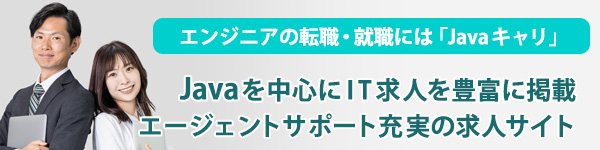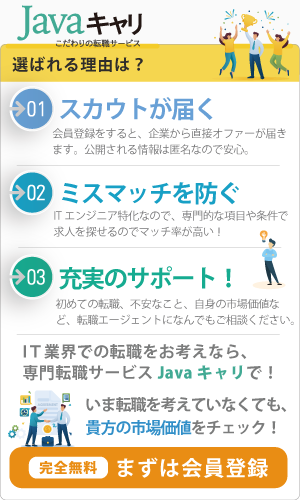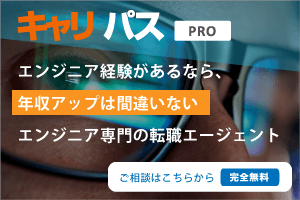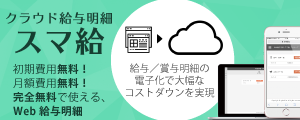システム開発において、ITエンジニア職であるシステムエンジニア(SE)とプログラマー(PG)は不可欠な存在です。
しかし、両者の役割を明確に理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。この記事では、SEとPGの具体的な仕事内容、求められるスキル、そして両者の連携の重要性について深掘りしていきます。
IT業界でキャリアアップを目指す方や、チームマネジメントに携わる方は、ぜひご一読ください。
■□■□プログラマーなどITエンジニアを目指しているならIT業界専門転職サイト「Javaキャリ」が最適!完全無料の会員登録はこちらから■□■□
Contents
システムエンジニア(SE)とプログラマー(PG)の違い
システムエンジニアとプログラマーの違いには、役割の範囲や必要な知識にあります。下記は、役割と知識の観点でシステムエンジニアとプログラマーの違いを比較しています。
| システムエンジニア | プログラマー | |
| 役割 | ・要件定義 ・基本設計 ・実装 ・テスト ・導入 ・運用/保守 ・ドキュメンテーション | ・実装 ・テスト |
| 知識 | ・基本的なプログラミング技術 ・設計スキル ・プロジェクト管理スキル ・コミュニケーション能力 | ・プログラミング言語の知識 ・フレームワークやライブラリの知識 |
システムエンジニアとは
システムエンジニアは、システム開発において要件定義をはじめとする上流工程を担当します。クライアントの要望をヒアリングして、システム仕様書を作成します。
知識については、専門的なプログラミングスキルよりも、プロジェクト管理スキルやコミュニケーション能力が重要視されます。実際、システムエンジニアがプログラミングすることもありますが、基本的にはプログラマーに依頼することがほとんどでしょう。
プログラマーとは
プログラマーは実装やテストなどの下流工程を担当します。システムエンジニアの作成した仕様書をもとに、プログラミング言語を用いてコーディングを行う職種です。知識については、専門的なプログラミングスキルやフレームワークやライブラリなどの知識が求められるでしょう。
システムエンジニアの仕事内容
システムエンジニアの仕事に就いてお話をする前に、ウォーターフォール型開発を採用したシステム開発の一般的な開発工程について解説いたします。
| 工程 | 内容 |
| 要件定義 | クライアントの要望に基づいてシステム全体の要件を明確にする。要件定義書という成果物を作成する。 |
| 設計 | システム全体のアーキテクチャ(基本設計)や機能の詳細な使用を設計(詳細設計)する。ここでは基本設計書と詳細設計書を作成する。 |
| 実装 | 詳細設計書に基づいて、コーディングする。プログラミングやデータベースの構築など。 |
| テスト | 完成したプログラムのテストを実施する。要件定義で定義された要件を満たしているかをテストする。テストの種類には単体テスト→結合テスト→システムテストがある。 |
| リリース | システムをクライアントが使用する本番の環境にリリースする。 |
| 運用・保守 | 正常に動作しているかの監視やバックアップ管理、不具合の修正などを行う。 |
上記、システム開発の開発工程を踏まえ、システムエンジニアの仕事内容について、解説します。
システム開発のすべてに携わる役割
システムエンジニアの仕事内容は、前述したシステム開発の全工程に携わります。その中でも要件定義と設計はシステムエンジニアにとってメインの仕事内容です。
クライアントから業務状況や要望をヒアリングした上で、予算や人員を決定します。さらに作りたいものと実現できるものをまとめて要件定義書という成果物を作成します。
次に、システム全体のアーキテクチャ・データの入出力やデータベースの仕様・プログラムの動作などを詳細に設計し、プログラマーにコーディングを依頼します。
設計の際には、ソフトウェアだけでなくハードウェアを含めた設計も必要です。具体的には、何台のサーバーが必要なのかやネットワーク構成はどうするかなどです。ITシステムが動作する環境全体の構成を考える必要があります。 このように、システムエンジニアの仕事範囲は広く、その影響はプロジェクト全体におよびます。
システムエンジニアでもコーディングを行うことはありますが、基本的にはコーディングはプログラマーの仕事です。
プログラマーの仕事内容
プログラムを組む役割
SEが起こした仕様書をみて、それを実際のプログラムコードに置き換えプログラミングする(=コーディングという作業)のがプログラマーの主な仕事内容です。
コーディングしたプログラムが待値通りの動きをしているか確かめるテストも行い、バグやミスがあればコードを修正して、再度確認していく作業も行います。
テストを行う上では、システム上あるべき姿に整えたテストデータの準備も行い、テスト対象のプログラムが稼働できる環境を整える(基盤ではなく個別のテスト環境の準備)ことも行わなくてはなりません。
いわゆる「ITエンジニアはずっとパソコンに向かって作業している」というイメージが、そのままPGの業務の実際のものと近いでしょう。
システムエンジニアとプログラマーの年収の違い
ここでは、システムエンジニアとプログラマーの年収の違いについて解説します。
システムエンジニア
厚生労働省の令和4年賃金構造基本統計調査によると、システムエンジニアの平均年収は510万円です。ただし、平均年収は企業の規模やスキルによって大きな違いがあります。システムエンジニアは、クライアントとの折衝やプロジェクト進行と管理など、プログラマーよりも広い業務と多くの責任をになっているため、必然的にプログラマーの平均年収より高くなります。
プログラマー
プログラマーの平均年収は、446万円とシステムエンジニアと比べて50万円ほどの違いがあります。しかし、プログラマーはプログラミングを通してシステムを構築するプロです。習得しているスキルや知識によってこの平均年収は大きく変わるでしょう。例えば、AIや機械学習などの最先端技術を用いてシステムを開発できるプログラマーはIT業界において重宝される存在です。
システムエンジニアとプログラマーの将来性の違い

システムエンジニアとプログラマーの将来性の違いについて解説します。
システムエンジニアの将来性
IT業界全体が、人手不足という課題を抱えつつもシステムエンジニアは将来性の高い職種であると考えられます。クライアントが求めるシステムを設計できるシステムエンジニアの需要が今後減少することは考えにくいです。
また、現代のビジネスにおいて、IT業界は必要不可欠です。それと同時にシステムエンジニアの存在意義も高まっています。
プログラマーの将来性
AIの普及によってプログラマーは必要ないという意見もありますが、そうではありません。しかし、技術の進歩によって今後の需要が変化する可能性は否定できません。
とはいえ、2024年時点のAIはプログラマーの存在を脅かすレベルまで到達していません。そのため、これから数年程度で突然プログラマーの需要が減少する可能性は低いといえるでしょう。これからプログラマーとして需要を維持するためには、最新技術を扱えるようになる自己研鑽が必要です。
システムエンジニアやプログラマーになるには
システムエンジニアやプログラマーになるためには、必要なスキルを知っておくことや資格を習得することが近道です。ここではそれぞれの必要スキルやおすすめの資格を紹介します。
必要なスキル
システムエンジニアとプログラマーでは役割が異なります。役割が異なれば必要なスキルも変わってきます。ここではシステムエンジニアとプログラマーそれぞれに必要なスキルについて解説します。
システムエンジニア
システムエンジニアは、主に上流工程を担当するのが役割です。システムエンジニアが対象とするシステムはプロジェクトによって異なりますが、どのプロジェクトでも共通して必要なスキルは下記の通りです。
- プログラミングスキル
- 論理的思考力
- ヒアリング能力
- 提案力
- 問題解決能力
- コミュニケーション能力
- プロジェクト管理スキル
システムエンジニアが直接コーディングする場面はそれほど多くないかもしれませんが、クライアントの要望に対して実現可能なのかどうかを判断するためにはプログラミングスキルが必要です。
また、ヒアリング能力と提案力はセットで重要なスキルです。ヒアリングした内容をもとにクライアントに対して提案するためです。
プログラマー
プログラマーには下記のようなスキルが必要です。
- プログラミングスキル
- デバッグスキル
- 論理的思考能力
- コミュニケーション能力
- 情報収集力
プログラマーはプログラミングをすることが役割です。そのため、プログラミングスキルは必要不可欠です。企業やプロジェクトによって求められるレベルは異なります。数年以上の経験が求められるプロジェクトの場合は、特定のフレームワークを扱えるスキルや、パフォーマンス向上ができるスキルが求められることが多いでしょう。
デバッグは、プログラムにあるバグを検知して修正する作業のことです。デバッグは実装段階で行うもので、構築されているシステムが複雑であればあるほどデバッグは必要なスキルです。
プログラマーはクライアントとの折衝がほとんどないため、コミュニケーション能力は必要ないと思われがちですが、他部署のチームやシステムエンジニアとの意思疎通のためにもコミュニケーション能力は必要です。
プログラマーが専門に扱うプログラミングの分野では、新しい開発手法やフレームワーク、技術が次々に誕生しています。新しい技術を活用できるプログラマーは企業にとって貴重な存在であるため評価されるでしょう。そのような新しい何かを習得するためには、情報収集が欠かせません。そのため、プログラマーには情報収集力が必要です。
おすすめの資格
IT業界でのキャリアを目指す上で、資格は必須ではありません。しかし、資格を持っていることでスキルの証明になるため、転職では有利にはたらきます。ここではシステムエンジニアとプログラマーそれぞれのおすすめの資格について紹介します。
システムエンジニア
システムエンジニアにおすすめの資格は以下の2つです。
- 基本情報技術者試験
- 情報セキュリティマネジメント試験
基本情報技術者試験は、ITを活用したサービスや製品、ソフトウェアを開発するIT技術者向けの試験です。情報技術の基礎やプログラミング・ネットワーク・データベース・セキュリティなどの基本が試験範囲となっています。難易度としては初級レベルですが、システムエンジニアとしてのキャリアアップを考えている人におすすめの資格です。
情報セキュリティマネジメント試験は、サイバー攻撃などの脅威からシステムや組織を守るための知識が問われる試験です。サイバー攻撃の種類や手法・セキュリティ技術や具体的な対策方法などが試験範囲となっています。実務ベースの事例を問題にして出題される傾向が強いため、IT業界に従事したことがない人には難易度は高いでしょう。しかし、システム設計を担当するシステムエンジニアにとって情報セキュリティの知識は重要であるため、この資格をもつシステムエンジニアは重宝されるでしょう。
プログラマー
プログラマーにおすすめの資格は扱うプログラミングによって異なりますが、ここではPHPとJavaの資格を紹介します。
- PHP技術者認定試験
- Java SE 8 認定資格
PHP技術者認定試験は、PHPに特化した資格です。PHPはWebアプリケーションを始めとするさまざまな開発で採用されているプログラミング言語で、需要が高い言語の1つです。試験のレベルには3段階あり、初級以外は難易度が高い試験となっています。まずは初級からチャレンジし、上級の試験を受けるのをおすすめします。
Java SE 8 認定資格は、基本的なプログラミング知識を有している証明となる資格です。国内だけでなく海外でも認知されている試験の1つであるため、将来的には海外で活躍したいと考えている人におすすめです。
システムエンジニアとプログラマーの違いを理解してキャリアに生かそう
今回は、これからシステムエンジニアやプログラマーになりたいと考えている人に向けて、それぞれの違いについて解説しました。
システムエンジニアはシステム開発において主に上流工程を担当し、プログラマーは下流工程を担当する職種です。それぞれ役割やスキルは異なるため、自分の目指すキャリアに合わせて資格の習得や学習が必要となるでしょう。
どちらも将来性は高いといえますが、やりがいを持って、続けるためには継続的なスキルアップが必要です。