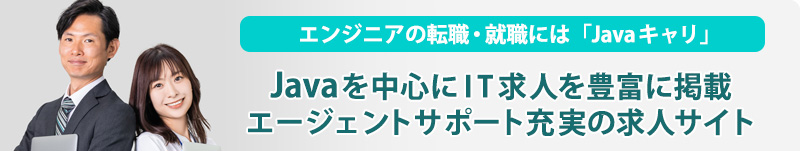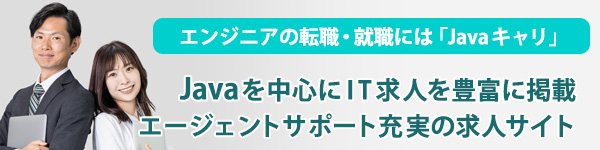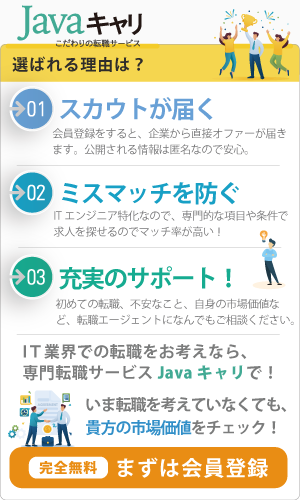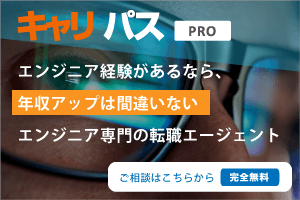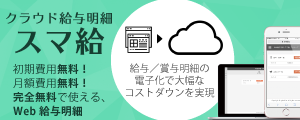コロナ禍を経て大半のITエンジニアは在宅勤務(テレワーク)を経験した事があると思います。
しかし、職場環境における働き方が変わってしまったことにより不安感が高まったり、インフラが整っていないため仕事の効率が上がらなかったりなど、様々な理由で退職を検討された方も少なくないのではないでしょうか。
2023年にはコロナ禍もあけたことで、リモートワークと出勤の併用だったり、完全に出社型に移行したりする企業が増えてきています。フルリモートの働き方も定着しており、減ってはいますがフルリモート求人も人気があります。
また、リモートワークが快適だったのに、会社の方針で出社型の勤務に戻ることになったことにより、リモートワークを実施している企業へ転職を検討するという人もいるようです。
本稿では、テレワークで在宅勤務中に退職するにはどうすればいいのか、通常勤務の場合との違いをご紹介します。是非ご参考ください。
■□■□プログラマーなどITエンジニアを目指しているならIT業界専門転職サイト「Javaキャリ」が最適!完全無料の会員登録はこちらから■□■□
Contents
在宅勤務での退職を決意したら
テレワークの導入中に退職を決意される方も多いのではないでしょうか。
退職を決意されるのには様々な理由があるかと思います。例えば働き方が変わった結果、新たなライフスタイルを選ぶことにしたというポジティブな理由から、インフラの整備や同僚とのコミュニケーションの違い、会社との距離を感じてしまい不公平感や不安感が増してしまうというものがあります。
また、退職することを決めておらず、誰かに相談したいという場合も、リモートワークですとWebミーティングでのコミュニケーションとなり、うまく相談できないといったジレンマがあるかもしれません。そのため、まだ迷っているが退職してしまうと決断する人もいるようです。
このように在宅勤務の最中に退職を決意された場合に注意しなければならないのは、通常勤務の場合との退職方法の違いです。退職方法が違うことを理解しなかった結果、余計な禍根を残してしまったり、退職方法が違うことを理解するのに戸惑ってしまった結果、退職を踏みとどまってしまったりすることを避けるためにも在宅勤務の退職方法をしっかり理解しておきましょう。
在宅勤務の退職方法 とは

退職の大きな流れは通常勤務と変わりません。在宅勤務の場合も通常通りのステップを踏むようにしましょう。
しかし、リモートワークの場合は直接のコミュニケーションに差し支えがあるため、退職の意志の伝え方や健康保険証などの会社への返却物の手配などが大きく変わってきます。
退職までの大きな流れは、下記になります。
- 退職を伝える相手をリストアップし、退職の意志を伝えます。
- 退職時期を調整し、引き継ぎなどを行います。
- 退職の手続きをします。
それぞれのステップで、特に在宅勤務の場合の注意点を中心にご紹介します。
退職の意思を伝える
在宅勤務の場合、出社して退職の意思を伝えるのが難しいかと思います。
しかし、だからといっていきなり人事部に退職の意志を伝えるのでは、禍根が残りかねません。特にエンジニアの場合、退職した後も企業が違えど別のプロジェクトで現在の同僚と一緒になることも少なくありません。そのため円満に退職することを意識しましょう。
まず、直属の上司やプロジェクトマネージャーなど退職を伝えるべき相手をリストアップし、退職の意志を伝えましょう。その際、退職の意志を伝えるのに、LINEやチャット、メールではなく電話をすることがおすすめです。
メールやLINEなどでの退職届も有効ではありますが、一方的な通知となってしまったり、相手の感情を知らず無駄に溝が広がってしまったりという可能性があります。可能な限り直接会話をして、自分の意志をしっかり伝えましょう。
また、電話する前に事前にアポイントを取っておくようにすることもおすすめです。ネガティブな理由での退職だとしても、相手の立場を考えるようにしましょう。
電話で退職の意思を伝えた後は、しっかり退職届を用意するようにしましょう。この場合もLINEやメールではなく、しっかり書面で用意することをおすすめします。なぜなら、退職後にハローワークにて離職票の発行手続きなどで退職届が書面で必要になる場合があるからです。
在宅勤務の場合はどうしてもメールやチャットで済ませてしまいたいと思いがちですが、しっかりと会話で伝えた上で書面を用意することを意識しましょう。
退職時期を調整し、引き継ぎなどを行います。

退職の意志を伝えたら、退職の時期を調整するようにしましょう。在宅勤務となって一人で作業をしていることが多くなったとしても、自己判断だけで決めてはいけません。プロジェクトマネージャーや上司と相談しながら、退職時期を決めましょう。
退職時期を決める際に気をつけるべき点としては、現在関わっているプロジェクトや契約の状況、引き継ぎに関わる期間を確認しましょう。プロジェクトを抜けるタイミングを誤ると他のスタッフに負担をかけることとなります。
上述したように、エンジニアとして転職する場合は同僚とどこで一緒になるかわかりません。なるべく負担がかからないことを意識しましょう。
退職の手続きをします
退職期間が決まったら、最終的な退職の手続きを進めましょう。退職にあたっては、会社に返却が必要な物と、逆に自分が受け取る必要がある物があります。
返却が必要なものとしては、健康保険証や社員証、支給されたパソコンなどがあります。定期券や名刺などの会社から支給された物は一通り返却について確認しておきましょう。逆に受け取るものとしては、年金手帳や離職票などがあります。
通常勤務の場合は出社して返却や受け取ることになりますが、在宅勤務の場合は郵送(宅配便)での送付でいいのかなどをしっかり確認しましょう。
特にパソコンなどは機密情報が含まれているため、退職後も保有している場合は損害賠償などに繋がるケースもありますし、配送中に破損させると責任問題でトラブルに繋がります。きちんと手順を確認した上で、自衛のために自身で対応できる範囲でしっかり対応しましょう。
また、退職の手続きチェックリストについて、更に詳しく知りたい場合は「退職手続きチェックリスト!返却物や受領物、その後の流れとは」をご覧ください。
退職代行サービスの利用について
近年退職代行サービスが増えてきており、Googleなどで検索すると多くのサービスを見かけるかと思います。在宅勤務の退職の場合、退職代行サービスの利用することはどうなのでしょうか。
本稿では、基本的には退職代行サービスの利用はおすすめしません。
上述したようにエンジニアとしての転職を検討している場合、同僚が転職したり、共同プロジェクトなどで今のメンバーとまた一緒なったりと、同じプロジェクトで作業する機会がいつ訪れるかわかりません。そのため、狭い業界内で退職のトラブルは起こさないことをおすすめします。
退職代行サービスによっては交渉・調整の余地が少ない転職になったり、退職時の引き継ぎ業務などが適切に行われなかったり、といったトラブルが残る可能性があります。 どうしても退職に同意してもらえない等、不当な理由で退職することができないような問題があった場合にのみ利用を検討しましょう。
2023年1月現在のリモートワークの動向
現在、新型コロナウィルスは春には落ち着きをみせてきて、このまま収束するのではないかという想いの方も多かった方と思います。しかし、10月以降新型コロナの感染者数は急激に増加しており、2023年1月には東京都の1日あたりの感染者数も1万人前後と高い数値の状況になっていますが減少傾向であることが伺えます。
しかし、政府の動向は経済活動をなるべく止めないという指針のもと、5類に引き下げる方針を固めたようです。
では、企業の在宅勤務(リモートワーク)の状況はどうなのでしょうか。日本生産性本部の「働く人の意識調査」が2022年10月後半に発表されましたが、テレワーク実施率がかなり低い17.2%という結果になりましたが前回よりは1%増加という結果になりました。リモートワークを牽引していた大企業が従業員規模別を問わず前回を下回るという結果がでています。すなわち、企業全体としてテレワークは縮小の傾向にあると考えられます。
以前はニューノーマルな働き方ということばがトレンドになっていましたが、いまの状況は、コロナが収束するアフターコロナには、コロナ以前のような出社型の働き方に戻るのではないかいう見解もあります。
しかし、一部の企業ではリモートワークによる生産性の向上を確立、各種手続きなどのデジタル化などを活用することにより効率的な環境を構築しており、アフターコロナ後もリモートワーク中心の働き方が継続される見込みであるようです。
リモートワークが新しい生活様式として定着することは難しいという結果になりつつありますが、コロナ禍の一時的な対策としてではなく、働き方の選択肢として活用していくべきだと思われます。
リモートワークに固執して退職を決めない方がいい
勤めているIT企業がリモートワークから出社型中心に戻ってきたが、自分はリモートワークで働きたいから転職を決断したというケースもあるでしょう。
しかし、リモートワークで働くことを条件にするのであれば、思わぬリスクがあることは理解しておいた方がいいでしょう。
例えば下記のようなリスクが考えられます。
- 転職先の企業が今後もテレワークを継続する保証がない
- 転職後もリモートワークのため帰属意識がなく会社に愛着が持てない
- 同僚と対面でのコミュニケーションがなく人間関係が希薄
- リモートワーク中心の企業だが評価制度が不透明で将来が不安
リモートワークで在宅勤務というのは一見すると通勤時間もなく効率的に思えますが、これまでのコミュニケーション方式は通用せず、新たなコミュニケーションツールを駆使し、コミュニケーションを補完しなくてはなりませんので、リモートワークを継続することのメリット・デメリットを把握した上で、働き方を選択するようにしましょう。
地方在住でリモートワーク実施企業への転職
IT企業はパソコンさえあれば、開発できる環境を準備できるということもあって、テレワークとの親和性が高く、成果を数値として捉えやすいことからも生産性をあまり下げずのテレワークを実現できるため、他業種と比較してもテレワーク導入率が高いのです。
こうした時代的背景とあわせ、地方創生を掲げる政、『移住者に最大100万円支給する』という移住支援金の配布対象を拡大するなどの動きもテレワークで地方に住み、都心の企業に属す働き方が事実上推奨される形となったことが背景にあります。
地方でITエンジニアが転職を検討できる求人は少ないため、転職することを諦めていた人も多いと思いますが、リモートワークが導入されたことにより、地方在住者であっても都心の企業にリモートワークで転職できるような求人が増えています。
地方にお住まいの方や、地方に住んでみたいと思っている方にとっては、新たな転職の選択肢となっています。
お勤めの企業から都心の企業へと転職をする際にも注意が必要です。なぜなら、入社するまでも、入社後も基本的には出社することはないでしょうから、会社の社風や雰囲気を肌で感じることが乏しいのです。
フルリモートで都心の企業への転職を考えている場合は、コミュニケーション対策などを手掛けていて、出社型以上にケアされている企業であるかを確認しておきましょう。また、フルリモート企業に転職する場合、心掛けとしてはフリーランスになったと同様の気持ちでいるといいでしょう。
地方と都心の企業は想像以上に相違点が多いので、転職先としての企業選定は納得いくまで突き詰めた方がミスマッチリスクが軽減されます。
新たな働き方を目指して最適な転職が実現できるよう頑張ってください。
また、地方在住で都心の企業へリモートで転職を検討さている人で、更に詳しく知りたい場合は「地方在住でフルリモート東京IT企業勤務の現状とはリモートワーク時に注意するべき3つのポイント」をご覧ください。
リモートワークでも転職することは問題ない
2025年現在、完全に出社型か週2回は出社してあとはリモートワークというようなハイブリッドワークというように働き方の選択肢は増えて転職環境は変化してきています。その中でエンジニアの方も転職することで新たなライフスタイルの実現を目指す方、キャリアアップを目指して退職を検討している方もいらっしゃるかと思います。
在宅勤務の場合も退職の流れは通常勤務の場合と変わりませんがコミュニケーションが取りづらいこともあり、やりとりには注意が必要です。また、エンジニアは狭い業界のため、円満な退職をすることは将来のプロジェクトにも大きく変わってきます。
在宅勤務では物理的に同僚が対面で周りにいないため、コミュニケーションは通常勤務と比べてより慎重に進めることがおすすめです。
円満な退職をすすめて、後悔なき転職活動を進め最適な企業へ転職を実現してください。